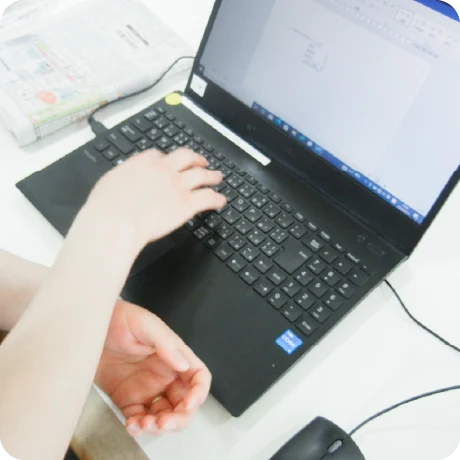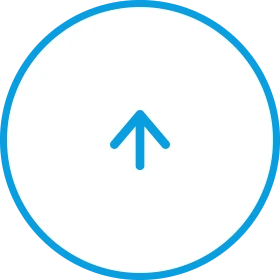Rehabilitation
生活期リハビリテーション
みなさんの笑顔をもとめて
医療療養病棟・介護医療院では、安心・安全な生活を送れるように支援しています。豊かな生活を目指して、身体機能の維持、生活の満足・充実を目指します。
医療療養病棟

医療療養病棟とは、急性期の治療を終えても、引き続き医療提供の必要度が高く、病院での療養が継続的に必要な患者さんを対象とする病棟です。
当院の医療療養病棟におけるリハビリテーションでは、「その人らしい生活を送る」「出来ることは自分の力で」「尊厳のある生活を送ることが出来る」ことを目標に豊かな生活が送れるよう、1人1人に応じた明確な目標を立てリハビリテーションを実施しています。
医師・看護師・介護士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・医療ソーシャルワーカー等が連携し、支援を行います。
状態が安定し、在宅や施設への転院が可能となった方には、退院支援も行っています。
介護保険分野のスタッフとも連携を取りながら、患者さんに応じた退院支援を実施しています。
介護医療院

介護医療院の最大の特徴は、「住まい」であり「在宅施設」である点です。
入所される方は、要介護者であり、急性期病院からも、回復期リハビリテーション病棟からも、入所してこられます。そして、従来の療養病床よりも充実したリハビリが実施できます。
したがって、回復期リハビリテーション病棟を退院後も、継続してリハビリを続けたい方も入所されてきます。
そして、自宅へ帰っていただく...そのような方も入所されます。
実際には、現在の多くの方が、介護度が重く、介護医療院を「終の棲家」としてご利用されていることは事実ですが、少しでも入所者の思いを受け止め、自分らしさを取り戻す手助けができればと思います。